フランシス・ベーコン『ベーコン随想集』
今回紹介する本はこんな人におすすめ⇩⇩
- 歴史哲学、言語学、文学理論に関心があるけれど何から読んでいいか分からない!
- 「はじめてだけど学問的な本を読んでみようかな」と思っている前途洋々な高校生・大学生
- 最近脳みそが停滞しているから知的な興奮を味わいたい奇特な社会人
Hello World! D氏です。
突然だが、サブタイトルに【教養を身に付けよう】とあるけれど、これはなにも読者諸賢に向けた啓蒙では必ずしもない。
実のところD氏自身がまずとても無教養である。
あるところで元東大教授の哲学者 野矢 茂樹 氏がこう書いていた。
(自身のことを指して)実は、とても無教養である。実のところ「教養」の意味すらよく知らないのだが、ともかくものを知らない。博識すなわち教養というわけではないにしても、ほどというものがある。シャレにならない。できれば隠しておきたかった事実である。生来、知識を増やすことにあまり関心がなかった。本もあまり読まなかった。いまもけっして読書家ではない。
かつて日本の最高学府で教鞭を執った哲学者によるソクラテスばりの謙遜と、実際に教養のない路傍の石コロたるD氏を並列する気はさらさらないけれど、この言葉はそのまま本記事の序文としてD氏の実感を言い得ている。
知識を増やすことに関心がなく、本もあまり読まず、いまもけっして読書家ではないけれど、願わくは「教養」だけは身に付けて世間にひゃあひゃあ言われたいと思っている。
しかしそんなにたやすく身につく教養などないのであって、そこはやはり本を読むしかない。
そう思ったときまず何から手に取るべきか? 言うまでもなく、新書である。
本の中でも新書という形態は、なにより安価で手に取りやすく、かつその分野の一流の専門家が初学者を想定して言葉や表現に精一杯の工夫を凝らしている場合が多い。
今回は言わずと知れた新書レーベル「岩波新書」から、個人的に「これは!」と思うおすすめの3冊を紹介する。
歴史ある岩波新書とくれば、そこから出版されるだけである一定の質的な保証がされていると言ってよいが、以下で紹介する3冊のおもしろさは際立っている。
どのような観点でおもしろいのか? その視点も含めて概要を解説していく。
これを今読んでいるあなたの知的好奇心にとってほんの少しでもきっかけになれれば幸甚。

目次
Ⅰ.E.H.カー『歴史とは何か』―歴史の本質を考える歴史哲学入門―
Ⅰ-1.『歴史とは何か』の概要と問題意識
おすすめの1作目はE・H・カー『歴史とは何か』(1962)である。
D氏はかつて、【書評】佐藤 究『Ank: a mirroring ape』―人類の起源に迫る自我意識の謎【魅力を徹底解説!】という記事の中で「私たちには、自らを位置付けたいという根源的な欲求がある」と書いたことがある。
これは表現を変えれば、自分とは何者なのか? どういった存在なのか? 世界はどうしてこう在るのか? というきわめて本質的な問いに対する納得できる説明を探し求める欲求があるということである。
D氏が「歴史」というものに関心を抱くとき、もっぱらそういう観点に立っている。
私たちの価値観や行動規範、判断基準、感性、認識その他あらゆる自分の構成要素は、私たちが生きる「いま、ここ」にある「この」時代に巨大な影響を受けざるを得ない。
いや、「影響」という言葉では本来不十分で、われわれはその時代に「埋め込まれた embed」存在である。
望んだわけでも選んだわけでもなく、単なる偶然(あるいは運命!)によって生まれ落ちた時代や場所すなわち環境(あるいはフッサールのいう「生活世界」)から不可避的に与えられる規制・制約(=枠)を脱することができない。それがわれわれ人間という存在である。
そう考えた時、私たちが生きるこの時代は一体どのような歴史的な流れの上に成立しているのか? という関心を呼び起こさずにおかない。
がそこで素直に「よし!歴史を勉強しよう!」と思えないところがD氏の唾棄すべき性質である。幸せになれそうにない。D氏はこう思う。
 D氏
D氏
つまり、「そもそも《歴史》ってなんなのだろう?」という根本的な問いに直面するのである。
外交問題ではしばしば「歴史認識」という言葉が用いられるが、地政学的な軋轢というのは世界各国で暮らす人々の間において「歴史」の捉え方がが異なっているために生じる。
それはすなわち、客観的で、統一的で、万人に受け入れられる「歴史」が存在しないことの証明でもあるのだ。
少し考えてみればわかる。私たちが学んだ歴史の教科書にはどういう歴史が書いてあったか? それはお隣の中国や韓国、あるいは西欧、中東、アフリカ、アメリカの歴史教科書とどう違うか? 違うとすればなぜ違うのか? それぞれの国によって異なる歴史を学ばせている結果、世界は現在どうなっているか?
≪真の歴史≫というものがあり得ないとして、我々が学ぶ「歴史」とはいったいどういった性質の文章なのだろうか?
そういった問題を考えるうえで真っ先に手に取るべき歴史哲学の入門書こそがE・H・カー『歴史とは何か』である。
■著者について
さて、本題に入る前に簡単に著者を紹介しておこう。
E・H・カーは1892年英国・ロンドン生まれの歴史家、国際政治学者だ。1916年ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ卒業後、外務省で外交官として1936年まで勤務。退官後は学界に入り、ウェールズ大学、オックスフォード大学で政治学を講じ、1955年からは母校のケンブリッジ大学トリニティ・カレッジの特別研究員となった。
■目次と概要
『歴史とは何か』の目次は以下の通りである。
Ⅰ 歴史家と事実
Ⅱ 社会と個人
Ⅲ 歴史と科学と道徳
Ⅳ 歴史における因果関係
Ⅴ 進歩としての歴史
Ⅵ 広がる地平線
本書『歴史とは何か』(原題:WHAT IS HISTORY?)は、1961年1~3月にかけてケンブリッジ大学で行われた連続講演がのちに書物としてまとめられたものである。
Ⅰ-2.「歴史」記述における事実と解釈
本書では各章のいたるところで歴史を中心とした非常に興味深い議論が展開されている。
それらの詳細をここで解説するには私の根気と時間が足りなそうなので別の機会に譲りたいと思うが、第Ⅰ章を概説するだけでもその立ち位置は伝わることと思う。
■「Ⅰ 歴史家と事実」の議論の流れ
カーはまず、歴史家によって考えられてきた「歴史」というものへの見方が二つの立場に大別されることを整理している。
【歴史の見方①】
ざっくり19世紀までを「事実尊重の時代」と呼ぶ。歴史家の姿勢は「ただ本当の事実を示すだけ!」という受動的なものであり、「事実」は観察者から独立して存在していると考えていた。科学的なものの見方が学界の主流を占めるようになり、〈事実〉から〈結論〉を引き出すべしという実証主義的歴史観が支配的潮流だった。
歴史は、確かめられた事実の集成から成っていて、歴史家は「事実」を文書や碑文などから容易に手に入れることができるのだった。
ここでは歴史とは、議論の余地のない客観的事実を出来るだけ多く編纂することなのだ。
【歴史の見方②】
19世紀以降の歴史観は上記の「事実尊重」のアンチテーゼとして確立した。そこでは「事実というのは、歴史家が事実に呼びかけた時にだけ語るもの」(p.8)と考えられた。「いかなる事実に、また、いかなる順序、いかなる文脈で発言を許すかを決めるのは歴史家なの」(同上)だ。
例えば、私たちが日常の中で歯を磨いたり通学通勤したりする。それは「事実」という意味では“ロシアとウクライナが戦争状態に入った”というものとなんら異なるものではない。だが、歴史家が“あなたが今朝歯磨きした”という事実を〈歴史的事実〉として捉えることはない。
つまり歴史的事実として現在(あるいは未来)に遺されるものには必ずなんらかの「判断」と「解釈」が加えられている。
その代表としてカーがやり玉に挙げるが「コングリウッド史観」である。コングリウッド(1889-1943 オックスフォードの哲学者・歴史家)は「単なる事実の編纂が歴史である」という歴史観から真逆に針を振って、「客観的」な歴史的真理など存在しないという結論を引き出した。
カーは上記の歴史観それぞれに問題点があり「支持し難いもの」と断ずる。
見方①は「そもそも古代史や中世史の記録には脱漏が散在して」いるので素朴に事実と受け取るのは論外。何より「歴史」として現在に残されたあらゆる文書自体が、当時知的に影響力を持ちえた少数者の意見を反映しているものに過ぎない。
見方②は歴史記述における歴史家の役割を強調しすぎていて、その論理的帰結として「歴史を人間の脳髄の編み出したものと考える危い淵」(p.34)に近づくこととなる。
そして、その二つの歴史観の間でバランスを取るようにカーは結論する。
事実を持たぬ歴史家は根もありませんし、実も結びません。歴史家のいない事実は、生命もなく、意味もありません。そこで、「歴史とは何か」に対する私の最初のお答を申し上げることにいたしましょう。歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります。(『歴史とは何か』p.40)
カーの惚れ惚れするようなバランス感覚の良さが滲み出る言葉を本当はもっとたくさん引用したいのだけれど、長くなりすぎるので割愛します。
繰り返すが、ある出来事が「歴史に残る」かどうかは決して自然に決まるわけではない。その出来事を「歴史に残す」べきものであると歴史家が考えるかどうかによって決まるのである。
だが、そこに生じる「解釈」と「判断」の根底には常に事実が据えられていることを忘れてはならないのだ。
そしてどれほど優秀な個人であっても人間である限りは基本的に愚かで誤りをおかすものだから、その「解釈」と「判断」は常に批判・検討されなければならない。
もちろん、あなた自身の「解釈」と「判断」も含めて。
(ここで賢い人間は「『解釈』と『判断』を批判・検討しなければならないというのもまた、D氏の勝手な解釈と判断なのではないか?」と批判・検討する。)
Ⅱ.池上嘉彦『記号論への招待』―ことばの世界の奥深さへ―
Ⅱ-1.『記号論への招待』の概要と問題意識
おすすめの2作目は池上嘉彦『記号論への招待』(1984)である。
この本はD氏の言語学とりわけ「記号論」への関心を決定づけた一冊だ。その後、現在に至るもなおD氏はしつこく「言語」への興味を抱き続けているわけだけれど、その発想の原点には常に本書があって、繰り返し手に取り、そのたびに発見がある。
■著者について
池上 嘉彦氏は1934年京都府京都市生まれ。日本の言語学者である。
東京大学文学部英文科卒業後、1961年に同大学院人文科学研究科英語英文学専攻博士課程満期退学し、1963年より東京大学教養学部外国語学科専任講師に着任した。以後、助教授(現在でいうところの准教授)を経て、1986年度から1993年度にかけて東京大学教養学部の教授を務めた。
専門は記号論・意味論・詩学である。
2000年に設立された日本認知言語学会初代会長でもあり、日本認知言語学分野において知らぬ者のない権威だ。
参考
設立趣意書日本認知言語学会
どこぞのエライ人が言ったり書いたりしているからそれは正しいのだ! と即断するような態度は「教養」からもっとも遠いものだと思っている。
このホームページタイトルにもなっているとおり、《語る者ではなく、語られる話こそ》が重要であることを忘れてはいけない。
■目次
『記号論への招待』の目次は以下の通りである。
Ⅰ ことば再発見 ー言語から記号ヘー
Ⅱ 伝えるコミュニケーションと読みとるコミュニケーション ー伝達をめぐってー
Ⅲ 創る意味と創られる意味 ー意味作用をめぐってー
1 記号と意味作用
2 分節と意味作用
3 記号と統辞
4 「テクスト」と〈話す主体〉
Ⅳ 記号論の拡がり ー文化の解読のためにー
1 記号の「美的機能」から芸術記号論・詩学へ
2 文化記号論へ向けて
■概要と問題意識について
さて、D氏にとってこの本がどういった点で興味深いのか? その点について述べてみよう。
一般化(普遍化)された知識として提示されるのがいわゆる「学問」だが、その出発点には必ずきわめて個人的な興味関心や問題意識がある。
そうでなければ知識を追求するモチベーションなど湧いてこないし、なにより面白くない。いかに自分に引き寄せてものごとを捉えるかが本(小説でも学術書でも)を読むときのコツである。
で、D氏はかねてより「ことばの不思議さ」に魅せられてきた。小説を読んでいるとき、この目の前の紙に印されたインクの集まりがどうして私の心象にこうも豊饒な世界を作り上げられるのだろうか! ということが不思議でしょうがなかった19歳の冬。そこからあれこれ読んだり考えたりしてきた。
そこで出会った答えの一つが、この『記号論への招待』であった。
次章では本書をよりよく理解できるように基本的な概念を解説していこう。
Ⅱ-2.重要な議論を図解!
そもそもわれわれが日常の中で「記号」というとき、どういったイメージを持つだろうか?
例えば、進入禁止や落石注意などの交通標識、「+」(足す)や「-」(引く)、非常口(EXIT)の緑のマーク、あるいはテスト問題などで「正解はどれか。回答欄に記号を記入せよ」の選択肢として挙げられる(a)(b)(c)(d)、地図上の学校や山や郵便局を示す標識などがまっさきに思い浮かべられる「記号」だろう。
本書ではこういったものを「記号」の中でも「符号」と呼び、区別していることにまず注意されたい。
「符号」はいわば、何かの代用をしているに過ぎない。重要なのはその何かのほうで、それを実際に持ち出す代わりに、それと一対一に対応させられているものを便宜上使っているだけだ。
だが、現代の記号論で「記号」を考えるとき、上記のような慣習的に正確に規定された内容の単純な「代用品」としての記号(=符号)を指しているのではない。
では、記号論で扱う記号とはどのようなものなのか?
これもまた具体例をだしてみよう。例えば、何らかの内容の代わりとなるのが「記号」だとしたら、その最たるものは「言葉」である。
ここで私が「オレンジ色のゾウがカリブ海を泳いでいる」と書く。
するとこれを読んでいるあなたの脳内では、見たこともない、存在するはずもないオレンジのゾウがサバンナを遠く離れた海で器用に鼻を出して海を渡るイメージが展開される。
このとき、「オレンジ」という言葉はこの色の代わりを、
そして「ゾウ」という言葉はこの動物

の代わりを(この写真もまた「記号」なのだが)、
「カリブ海」という言葉はこういう場所

の代わりとしての役割を果たす。
しかしこの時、重要なのは「ゾウ」そのものや「カリブ海」そのものだろうか?
いや、ちがう。
一般的なわれわれの知識と照らし合わせて信じがたいようなイメージを呼び起こす「オレンジ色のゾウがカリブ海を泳いでいる」という「言葉」そのものこそ、注目すべきものなのだ。
「この発言は嘘なのか?」「ファンタジーの物語世界の中での出来事なのか?」「ある学者による過去にありえた事象の仮説なのか?」など、「オレンジ色のゾウがカリブ海を泳いでいる」という「言葉」に与える文脈次第で実際の意味はいくらでも変わり得るけれども、ここでは《意味されるもの》に対して《意味するもの》すなわち「記号」の優位性が逆転していることを見て取れる。
交通標識などに代表される「符号」の固定性とはちがった位相で、「記号」は無限に多様な意味を持ちうる。
「記号論」とは、そういう豊かな「記号」を研究しようとする学問なのである。
いちばん基本になることは人間の「意味づけ」とでもいった行為――つまり、あるものにある意味を付したり、あるものからある意味を読みとったりする行為――である。人間が「意味あり」と認めるもの、それはすべて「記号」になるわけであり、そこには「記号現象」が生じている。この「言語創造」にも似た行為を、人間は絶えず、しかもその文化のあらゆる面で行なっている。その原型と本質を探ってみること――そこに現代の記号論は関心を向けるのである。人間の「意味づけ」する営みの仕組みと意義――その営みが人間の文化をいかに生み出し、維持し、そして組み変えていくか――現代の記号論はこういうことに関心を持っていると言いかえてもよいであろう。(『記号論への招待』p.5)
そういった「記号」観を前提したうえで、本書における重要で基本的な概念を図解したので参照してほしい。
①「意味伝達モデル」
「意味伝達」のモデル
私たちが生きるこの人間の世界でもっとも根底にあるのは「意味づけ」である。
「存在する」ということはすなわち「誰かになんらかの意味を与えられている」ということとイコールである。
では、われわれがある対象に「意味」を読み取るとはどういうことなのだろうか?
それを図示したのが上記である。
②「コミュニケーションにおける伝達の仕組み」
「伝達の仕組」
意味伝達にはあらゆる方法や形態があるけれども、その中でも人と人の間で行われる意味伝達、つまり「コミュニケーション」はどのように行われるか? を図示した。
例えば、A(男性)がB(女性)に「好き」という気持ち(=伝達内容)を伝えたいとする。
そのためにはまず、Aが彼の生きる文化圏で共有されているコードに則ってその気持ちを記号化しなければならない。
つまり「好き(suki)」と声に出したり、あるいは手紙に書いたり、その他、気持ちの代用を果たしうる記号を表現する(=メッセージ)。
その記号を受け取ったBが、彼女の持つコードによってそのメッセージを解読する。
「Aは私のことを好きなのか」という伝達内容を受け取る。
それがコミュニケーションと呼ばれるものの流れだ。
だが実際にはそこに「文脈 context」という重要な要素が入り込むのだが、ここではそこまで立ち入らない。
③「記号論における3つの研究分野」
記号論の研究分野
記号論は上の図のように3つの研究分野に大別される。
D氏個人でいえば、もっぱら「意味論」すなわち記号と指示物との関係性を研究することに関心がある。
例えば文学テクストを読み、そこにある文章の塊=記号がどういった指示物の代わりを果たしえているのか? また、それはどういった点で効果的な代わりを果たしているのか? そういうことを考えるのが好きだ。
いずれにしても、「記号」とはこの世に存在するすべての「意味作用」に関わるという意味で、小説・漫画・音楽・映画・絵画その他あらゆる文化的な産物の鑑賞や分析に適応できる学問であることは疑いない。
その点で『記号論への招待』はものごとをより深く見ていくために必読の一冊と言えるだろう。
Ⅲ.筒井康隆『本の森の狩人』―小説=物語を読みこなす技術―
Ⅲ-1.『本の森の狩人』の概要と視点
おすすめの3作目は筒井康隆『本の森の狩人』(1993)である。
D氏は文学から社会科学、自然科学、絵本、漫画、論文その他あらゆるジャンルの文章を読むけれど(少なくともそう心掛けているけれど)、何を隠そうそういう読書傾向を獲得したことは筒井 康隆 氏の影響を抜きに語ることができない。
筒井康隆は稀代の読書家であることは誰もが知る所であるけれども、彼はそれを「全方位性」と言っていた。
D氏の本棚にある本の内、著者別の冊数で最も多いのは筒井康隆であり、彼の指向性を内面化することでD氏の読書傾向は大いに規定されたところがあるのである。
SF作家としての印象が強いと思われる筒井康隆だが、案外小説以外にエッセイもたくさん出していて、D氏は彼のエッセイも大好きである。
ここで紹介する『本の森の狩人』は、筒井康隆に拠る文芸時評であり、「いかに現代文学を読みこなすか?」という観点から非常に参考となる一冊である。
■著者について
現代を生きる小説家の中で筒井康隆ほど著名な方もいないのでここで改めて紹介する必要もないと思われるが、形式上簡単にやらせていただきます。
筒井康隆は文化方面で長年、多面的に活躍されているからどこを切り取るかでその像も多様であるけれども、基本的には(SF)小説家・俳優・劇作家ということになっている。
つい最近、以下のような記事も出ていた。
代表作も年代やジャンルによって多数あって「これ!」と絞るのが難しいほどである。
しかし一般にはやはり『時をかける少女』の原作者といえば通りがいいのかもしれない。
自身、文学賞も色々とっているし、選考委員としても長年活躍してきた。つまり「書く」ことと並べて「読む」(鑑賞する)ことのプロなのである。
■目次と概要
『本の森の狩人』の目次は以下の通りである。
はじめに
第1回 アンドレ・ジッド「廣金つかい」
第2回 谷沢永一「回想 開高健」
第3回 久世光彦「花迷宮」「怖い絵」
第4回 ミラン・クンデラ「不滅」
第5回 大江健三郎「治療塔惑星」
第6回 J.G・バラード「ウォー・フィーバー/戦争然」
第7回 レイモン・クノー「イカロスの飛行」
第8回 丸山健二「千日の瑠璃」(一)
第9回 丸山健二「千日の瑠璃」(二)
第10回 関寿夫「現代芸術のエボック・エロイク」
第11回 河合隼雄「心理療法序説」
第12回 ディヴィッド・ロッジ「素敵な仕事」
第13回 ディーノ・ブッツァーティ「タタール人の砂漠」
第14回 アルトゥール・シュニッツラー「カサノヴァの帰還」
第15回 長部日出雄「愉快な撮影隊」
第16回 スティーヴ・エリクソン「ルビコン・ビーチ」
第17回 ティム・オブライエン「カチアートを追跡して」
第18回 中村隆資「地蔵記」
第19回 カート・ヴォネガット「ホーカス・ポーカス」
第20回 T・コラゲッサン・ボイル「イースト・イズ・イースト」
第21回 小林恭二「瓶の中の旅愁」
第22回 内海隆一郎「波多町」
第23回 小西嘉幸「テクストと表象」
第24回 井上ひさし「括弧の恋」
第25回 サバテール「物語作家の技法」
第26回 中上健次「軽蔑」
第27回 マルグリット・デュラス「愛人」
第28回 ジョン・バンヴィル「コペルニクス博士」
第29回 オールディス、ウィングローヴ「一兆年の宴」
第30回 清水義範「世界文学全集」
第31回 永井豪「オモライくん」
第32回 ジョルジュ・ペレック「人生 使用法」
第33回 辻邦生「江戸切絵図貼交屏風」
第34回 三枝和子「響子悪趣」
第35回 ゲオルグ・ユルマン「人がみな狼だった時」
第36回 藤原智美「運転士」
第37回 笠井潔「哲学者の密室」
第38回 島田修三「晴朗悲歌集」
第39回 筒井康隆「人がみな狼だった時」
第40回 ジャン・チュイリエ「眠りの魔術師・メスマー」
第41回 トオマス・マン「魔の山」
第42回 プリーモ・レーヴィ 「周期律—元素追想」
第43回 ウンベルト・エーコ 「ウンベルト・エーコの文体練習」
第44回 D・H・ロレンス「チャタレイ夫人の恋人」
第45回 マリオ・バルガス=リョサ「誰がパロミノ・モレーロを殺したか」
第46回 松村昌家編「子どものイメージ」
第47回 ジョルジュ・バタイユ「文学と悪」
第48回 トマス・ピンチョン「競売ナンバー9の叫び」
第49回 中条省平「最後のロマン主義者」
第50回 カルロス・フェンテス「遠い家族」
第51回 バルザック「従妹ベット」
本書『本の森の狩人』は、1992年に1年間にわたって『読売新聞』朝刊に連載された全52回の文芸批評コラムがまとめられたものである。
「文学部唯野教授の読書法・実践編」ともいうべき一冊であり、「さまざまなにスタイルの異なる小説が氾濫している現在、読者がそれらをどう判断すべきか、そのとりあえずの目安を提供」(「はじめに」より)している。
Ⅲ-2.筒井康隆流、批評の実践的技術を盗もう!
周知のように、筒井康隆は「文学理論」に極めて自覚的な作家として知られている。
それは書くときには『文学部唯野教授』やその他言語実験的な作品群に結実するのだが、読みに適用されると、深く作品を読解するツールとなる。
筒井康隆はその中でも「虚構性」という概念にこだわっていて、このコラムでもしばしば「虚構の虚構性」について思索が展開されている。
それが具体的にどういったものを示すのかについてはぜひ本書を手に取って体感していただきたいのだが、D氏なりの言葉でいえばそれはつまり「虚構であることが前提されている虚構」ということだ。
そういった点も含めて個人的に読みたいと思った、または実際に購入した本を扱っている回を紹介しよう。
■第9回 丸山健二「千日の瑠璃」(二)
筒井康隆氏が色んな場所で語る「感情移入批評」というものが具体的にわかる。
■第13回 ディーノ・ブッツァーティ「タタール人の砂漠」
筒井康隆が自身の創作への影響を公言している作家にフランツ・カフカがいるが、カフカは一般に「不条理文学」と評される。
では不条理文学とはなにか? ここで筒井康隆はその要件を2つ挙げている。
① 哲学的疑問を提示し、読者の真実を求める欲求を刺激する。
② 結末で、回答が与えられない。
■第16回 スティーヴ・エリクソン「ルビコン・ビーチ」
「この長編小説の第三話の主人公は、実際に方程式で自分の思い出を反証したり、太陽の存在を反証したり、個人的挫折を正当化したりするし、9と10の間にもうひとつ数があることを証明したりもする」(p.64)
この屁理屈めいたアイデアがおもしろい。
森見登美彦「大日本凡人會」の主人公「数学氏」を彷彿とさせる。
■第36回 藤原智美「運転士」&第42回 プリーモ・レーヴィ 「周期律—元素追想」
それぞれ、作家自身の職業への異常なこだわりを作品に昇華している点が称賛されていて、それこそ作家の資質であると語られていて興味深い。
「小説を書くというのは多かれ少なかれ自分の作った虚構に執着し、つまらないことへのこだわりや几帳面さを必要とする行為」(p.146)
以上、『本の森の狩人』の内容を簡単に紹介してきた。
繰り返しになるが、本書は読書案内として読んでもいいし、本の読み方の参考にしてもいい。扱われているのがやや古い本なので入手しづらいものもあるが、気になった本から新たに作家やジャンルを開拓するのもよいだろう。
そうやって読書の幅は広がっていくものなのだ。
まとめ
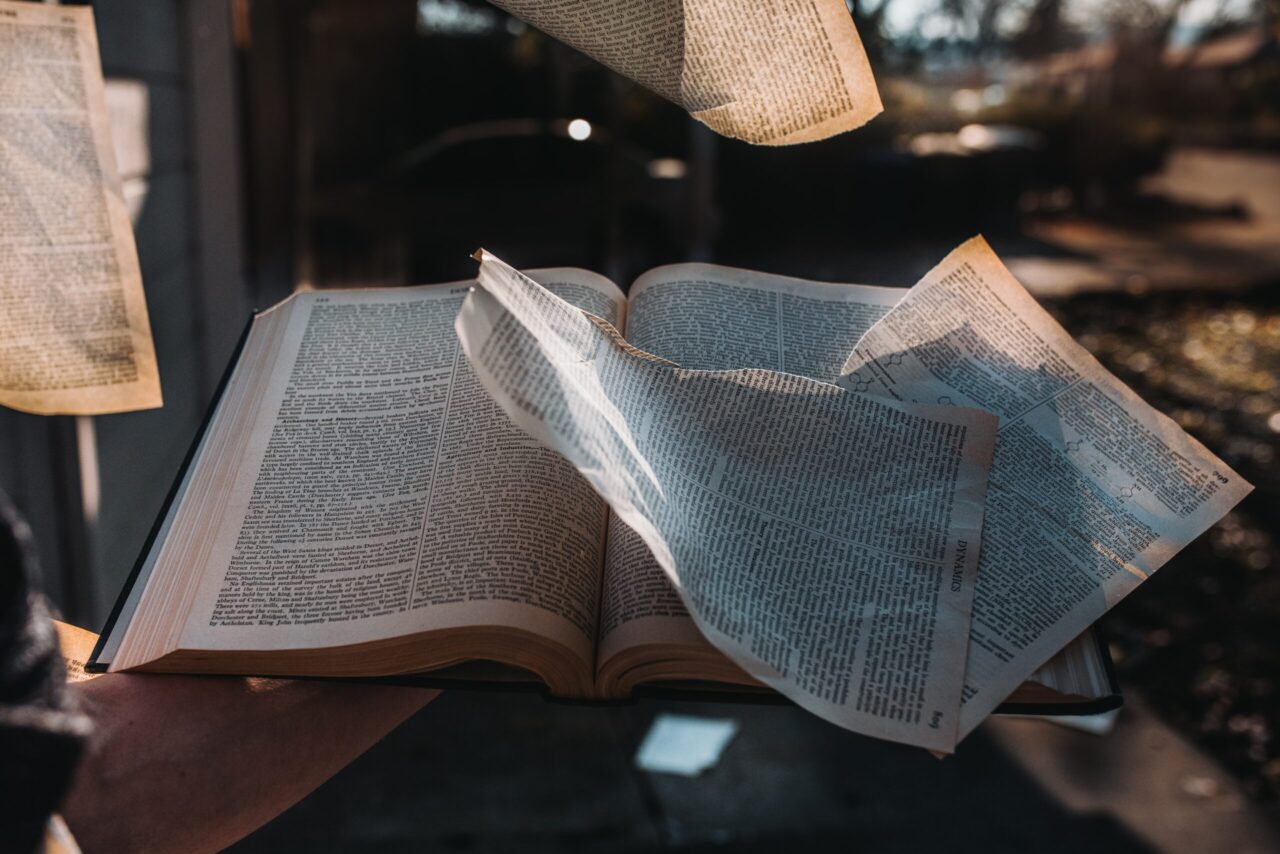
今回はD氏が特におすすめする岩波新書の3冊を紹介した。
冒頭で野矢 茂樹 氏の言葉を引用したけれど、彼はその文章の最後でこう書いている。
「ちぇっ、十代・二十代にもっと本を読んどきゃよかった。反省してる」
この間30歳になったD氏もまた、はなはだしく同感だと思っている。だが、まだ…まだ遅くない。こと「学び」において遅すぎるということはないのである。
読者諸賢においてもまた、以下略。
今後もD氏とともにあらゆる知識領域の扉を中途半端にこじ開けていこう。さすれば何某かの「教養」めいたものがあなたの脳内の片隅に産まれないとも限らない。保証はしない。
しかし信ずるものは救われる、という。ゆめゆめ疑うことなかれ。

