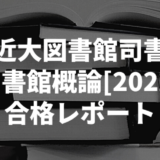『読む力は生きる力』
- 子どもに本を好きになってもらいたいと思っている子育て世代
- 「読書」をする必要性がいまいちよくわからない少年少女
- 心から子どもにおすすめできる児童文学が知りたい保育に関わるすべての人
私は読む本のジャンルにあまりこだわらない。「おもしろければなんだっていい」と考えるようなテキトーな読書人である。
例えばつい先日読み終えた一冊に舟崎 克彦『ぽっぺん先生と帰らずの沼』がある。
これは一般には小学生くらいを対象にしている本だと思うけれど、30歳のおっさんになった今の私が読んでも極めて前衛的でファンタジックな物語だと感心しきりである。
自分の行動や考え方に影響を与えてくれるような「いい本」との出会いは、紛れもなく人生を豊かにする。それはこれまでの読書経験によって獲得した直観である。
ところで、これまでに何度か述べている通り、私は現在図書館司書養成課程の勉強をしている。
そこで履修すべき科目の一つとして「児童サービス論」がある。これは0~18歳の年齢層を対象に行われるべき図書館サービスを学ぶものである。
そのテキストで紹介されていた参考図書の一冊に脇 明子『読む力は生きる力』があった。文脈から察せられるかと思うが、本書は子どもにとっての「読書」の意義を考えているエッセイである。
これは余談だが、私には天使と見まがうほどキュートな1歳の娘がいる。
私は彼女の記憶の基底を成すような素敵な物語をたくさん読み聞かせたいし、出会って欲しいと願っている。
そう考えたとき「読書とはそもそもなんなのか?」「読書はなぜ必要か?」といった根源的(ラディカル)な問いから逃れられない。
『読む力は生きる力』はそのような観点からなかなか示唆に富んでいるので今回紹介することにした。
目次
1.『読む力は生きる力』の概要

1-1.著者 脇 明子 について
脇 明子 氏(1948年-)は、ノートルダム清心女子大学名誉教授(元・人間生活学部 児童学科 教授)で、主にイギリスのファンタジーの研究、翻訳を専門とする児童文学者である。
訳書に、岩波少年文庫の『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』(ルイス・キャロル)や、『クリスマス・キャロル』(ディケンズ)などがあるので、若い方は案外知らず知らずのうちに彼女の文章と接しているかもしれない。
ツイッターではこんな評価もある。
『クリスマス・キャロル』の翻訳は多くあるが私は、岩波少年文庫の脇明子訳が、最もディケンズの世界をよく表現していると思う。ディケンズはこの物語を、日ごろ本を読まない人、あるいは幼い子どもたちにも読んでほしいと思って書いている。脇さんはそのことをよく理解し、日本語に移し替えている。
— 若松 英輔 (@yomutokaku) December 8, 2020
1-2.『読む力は生きる力』の作品情報
さて、本書は長年児童文学に携わってきた著者による、子どもにとっての「読書」の意義を考えている評論・エッセイである。
著者の言葉を借りれば、「『読むことはなぜ必要なのか』という原点にこだわりつづけてきた」ことで見えてきた「答え」をまとめたものである。
目次は以下の通り。
第1章 読むことはなぜ必要なのか
第2章 赤ちゃんと絵本
第3章 絵本という楽園の罠
第4章 「文字を読む」ことと「本を読む」こと
第5章 読めない理由
第6章 読書力とは何か
第7章 ほんとうにいい本を手渡すために
個人的には第4章~第6章が特に興味深かったので、以下ではそれらの章の内容に焦点を絞って紹介しよう。
2.『読む力は生きる力』の読書哲学

2-1.「本を読む」とはどういうことか?
早速本題に入るのだが、まず考えたいのは「本を読む」とはどういうことか? という、普段まっとうに生きている人間であれば思い浮かばないような問いについてである。
先でも触れたように、脇 明子 氏は大学で教鞭をとっていた方である。そこで彼女は、大学生の中でさえ読み書き能力にはなんら問題がないにも関わらず本が読めない子がざらにいる、という経験をした。
これはいったいどういうことなのか? 例えば、児童文学作品を読んでレポートを書く課題を出すと次のような意見が飛び出すという。
「読もうとは思っているのだが、どうしても身体が受けつけてくれなくて困った」
「途中でやめて、次に読もうとすると、内容がわからなくなる」
「読みはじめてもなかなか大きなことが起こらないので、結末を講義で聞いていなかったら、最初のほうで読むのをやめたかもしれない」
「自分は本を読むのには向いていない」
「読んでいても、本の内容が頭にきちんと入ってこず、すぐにだれとだれがどういう関係だったのかわからなくなり、頭のなかでごちゃごちゃし、前のページを行ったり来たりして、まったく進まず、イライラしてきて、おもしろくないと思い、けっきょく途中で挫折し、最後まで読めたものは少ない」
つまり、ここで指摘されているのは、「文字の読み書きができること」と「本を読めること」はイコールではないということなのである。
そしてそれは、子どもたちにしても同様だという。
私たちは、子どもたちに「字を読む」技術さえ習得させれば、「本を読む」ことは自然についてくると考えてはいないでしょうか。だとしたら、それは大きな思いちがいであるように思われます。「本を読む」うえで肝心なのは、一文字一文字を読むことではなく、言葉をもとに想像力を働かせ、内容を理解し、物語の展開についていくことです。(p.79)
私たちが文字をたどって本を読むという安易ならざる行為を続けていけるのは、読み進めるにつれて想像力が働き、文字から立ち上がる世界なり概念を心に描き始め、その世界やそこに住むキャラクターたち、あるいは展開の続きなどをもっとも知りたいという欲求がむくむくと湧いてくるからである。
しかし、そういう想像力を子どもが初めから持っているかというとそうではない。
さながら車やバイクのギアの1速のように、または飛行機の助走のように、どんな本でも読み始めはエネルギーがいる。そこを越えて軌道に乗れれば、あとは想像力が駆動し自分を未知の世界へと連れて行ってくれるものなのである。
だから、まだ読書に入り口にいる子どもや本に苦手意識を持つ中高生や青年(あるいは大人にも!)、最初はだれかが補助輪の役割を果たさないとならないのだ。
その本がどうおもしろいのかあらかじめ紹介したり、もしくは装幀や題名に心を惹かれたりするのもいい。目次がおもしろそうだったりして好奇心が刺激されることもある。
いずれにしても、何よりも大きな力になるのは、最初の退屈な何ページかをしんぼうして歩きだんだんおもしろくなってきて、しだいにやめられなくなり、最後には大の愛読書になったという体験を、ちゃんと持っているということです。(p.82)
憚りながら、私がこのブログで目指すものの一つが、そのような体験の入り口に立つお手伝いなのである。
2-2.短編小説と長編小説
本書における「本を読む」とは「言葉をもとに想像力を働かせ、内容を理解し、物語の展開についていくこと」であった。
そう定義したうえで、著者は短編小説と長編小説の違いについて述べる。そこには暗に、長編小説を読めるようになろうね! というメッセージが込めれられているように思う。
- 短編小説:短編のおもしろさは、核となるアイディアにかかっている。キャラクターや世界観が好きになれるほど丹念に描かれていないことが多い。アイデアが自分にハマれば大好きになれるが、そうでなければそれっきりになりがち。
- 長編小説:子どもが親友にしたくなるような主人公や、頼もしくてすてきな大人、ここに住みたいと思うような家や村などが、いきいきと描かれている。しっくりと心になじむ世界や人々が見つかれば、そこはいつでも遊びにいけるもうひとつの居場所、大好きな人たちが待っていてくれる、もうひとつの家になる。それを手に入れることができれば、世の中を渡っていくときの大きな支えになる。
もちろん短編小説にも長編小説にも色々あって、一概にすべてが上記の通りというわけではない。魅力的なキャラや世界観を提示している短編小説だって山ほどあるし、キレのあるアイデアで展開される長編小説だってももちろんある。
だが一般に、小説の短編・中編・長編という形式の違いによって重きを置くべきポイントが異なるのもまた事実である。そして、脇 明子 氏が言うように、自分の心の拠り所となるような作品はやはりディテールがよく書き込まれた長編小説であることが多いのだ。
子どもにとってそういう大切な“場所”となり得るような長編小説の例として、著者は以下の作品を挙げる。※()内、原作発表年
■ふたりのロッテ(1949)/エーリッヒ・ケストナー
■点子ちゃんとアントン(1931)/エーリッヒ・ケストナー
■大きな森の小さな家(1932)/ローラ・インガルス・ワイルダー
■小さい牛追い(1933)/マリー・ハムズン
■やかまし村の子どもたち(1947)/アストリッド・リンドグレーン
■おもしろ荘の子どもたち(1960)/アストリッド・リンドグレーン
■ドリトル先生航海記(1922)/ヒュー・ロフティング
子ども向けの本と侮らず、気になるものがあれば皆様自身がまず手に取ってみるとよいだろう。
(などと言いながら、私は上記のうち『点子ちゃんとアントン』『大きな森の小さな家』しか所有していない…)

2-3.「本を読むのはいいこと」なのか?
次の問いへ移ろう。
本書第6章では、一般的な通念としては無条件に受け入れられている「本を読むのはいいことである」という言説を検証している。
読書がいいのだとすれば、それはなぜか?
本当にいい本とはどんなものを指すのか?
読書が子どものためになるとはどういうことなのか?
脇 明子 氏はそこまで突き詰めて考えた上で子どもに働きかけないと逆効果になると指摘する。
「なんでもいいからたくさん」では、想像力や思考力を働かせて読むという力は身につきませんし、子どもが手に取る本の質は明らかに悪化します。(p.131)
そう考えたとき、さらに一歩手前のこんな疑問が頭をもたげてくる。
そもそも「読む力」を育てる必要はあるのか? なぜ本を読むことが必要なのか?
いかがであろう。このブログを今まさにそこで読んでいるあなたはこの問いに答えられますか? ただなんとなく子どもに本を読めと言っていませんか? あるいは自分はそういわれて育ってきてませんか? 学校で、朝の読書で、とにかくなんでもいいから読むように言われてなかったですか? その結果、あなたは「読書」から離れずに大人になれましたか? あるいはあなたの周囲に本を習慣的に読む人間がどれだけいますか? いませんか? いないのだとしたら、あなたや彼らはなぜ本好きにならなかったのですか? どうして本を読まずにテレビやスマホやSNSやゲームや漫画やアニメ・映画にばかり手が伸びるのですか? 第一、知識や楽しみを得るのに本以外の手段を使っても不都合ではないですよね。今ならYouTubeなんかで良質な教養動画もあるし、そもそも読書力なんかいらないはずでは?
そういう問いに対する脇 明子 氏の回答は実にシンプルである。
「本が一切に優先しないのは、心底おもしろいと思える読書経験を持っていないからだよ!!」
だから、子どもには本をちゃんと読みこなせば、マンガよりもアニメよりもゲームよりもおもしろいことを伝えていく必要がある。
それから著者は、幼児~青年期にかけて映像メディアや電子メディアが与える影響は、これまでに考えられていた以上に深刻である可能性があると述べる。
なぜなら、そこでは強烈な「イメージ」が否応なく鑑賞者に飛び込んできて彼らを押し流してしまうからである。そこに受け手の想像力が発揮される余地ない。けれどそれは楽で、快感で、きわめて誘惑的な経験である。
だが一方で、人々はそれらの「イメージ」に心底から感情移入し、愛着を持つことは多くない。たまたま本で気に入っていた小説などが映画化されたのを見て「イメージがちがう」とがっかりすることがよくあるが、それはなぜかというと、自分の内側から内発的に生まれてきたイメージこそ「真」であり、リアリティを感じるからである。結局人は、「自分」から逃れられない。他者によって「私にはこういう世界が見えているんだ!」と押し付けられて部分的に共感したとしても、やはりどこかに疎外感を抱く。
本と他のメディアとの決定的な違いはここにある。
物語がおもしろくて、想像力が自然に働きはじめると、登場人物たちの表情や声音はもちろんのこと、あたりの情景、空気、匂いなどといったものまでが、自分で体験していることのように、リアルに感じられることがあります。それに比べると、ほかのだれかの想像に基づく映像は、どれほど見事にできていても、しっくりこなくてあたりまえです。そんな経験を重ねれば、「映像のほうが常におもしろい」とは思わなくなり、自分で想像する自由を確保するためにメディアの誘惑をしりぞける力も身につくはずです。しかし、そうなるためには、おもしろくなって自然に想像力が働き、忘れがたいイメージを生じさせてくれるような本に、出合わなくてはなりません。読みやすいけれども中身の薄い本や、絵が多すぎて自分で、作れないような本では、その役には立たないのです。(p.135)
そして脇 明子 氏は言うのである。
ともあれ、夢見ることが困難な世の中で生きていくとき、物語で出会ったお気に入りの場所、お気に入りの人たち、お気に入りの台詞や場面をたくさん持っているというのは、じつに心強いことです。(p.138)
心の中を素敵なイメージで満たせれば、きっと人は人生を豊かに生き抜いていける。そんな著者の主張が感じられる一文である。
2-4.「読書力」とはどんな力か?
もう少し「なぜ本を読むことが必要なのか?」という問いに踏み込んでみよう。
映像ではけっして代用できない読書の価値は何か? それは読まれる内容にあるのではなく、読むという精神活動そのものにあると脇 明子 氏は考える。
では「読むという精神活動」によって涵養される能力はどのようなものなのだろうか? その能力を指して著者は「読書力」としている。
①書き言葉レベルの言葉を使う力
②想像力
③全体を見渡して論理的に考える力
2-4-1.書き言葉レベルの言葉を使う力
学生と社会人で顕著に異なるもののひとつは「言葉遣いの厳密性」であろう。
異なるバックグラウンドを持つ人間集団のなかでお金が絡む仕事を遂行しようと思えば、正確な言葉遣いが必要となる。特に「他人に伝わる文章」を書くためには、語彙も豊富であることが望ましい(と書いている私の文章が「他人に伝わる文章」なのか甚だ心許ないが…)。
また、書き言葉レベルの言葉を身につけるのは「明晰な思考」をする上でも必須である。
我々がものを考えるとき、頭の中ではもっぱら「言葉」を使っているからである。
言葉を知らないのに複雑な思考ができた、などとということはあり得ない。思考の明晰性は言葉の明晰性である。
それらは「読む」という経験値に支えられ、育てられるのである。
2-4-2.想像力
著者に拠れば、「想像力」とは「頭のなかにイメージを作りだす力」である。翻って言えばファンタスティックな内容を思い浮かべることではない。
では、「イメージ」とはなにか? それは「その場に実在しないものの視覚的な像」である。
例えば、目の前にいない友人の顔を思い浮かべたりするというような些細なことでも、それはイメージである。したがって何ら特別な能力ではない。
特別ではないが、人生を渡っていくために重要な能力ではある。なぜか?
コミュニケーションをとるとき、相手の目には物事がどう見えているかが推測できれば、ひじょうに役に立ちます。相手の微妙な感情や隠し持った考えを推測するとなると、かなり高度な想像力が必要ですが、用件を伝えたり説明をしたりするとき、相手がどんな情報を必要としているかを推しはかるくらいなら、単に相手の視点に立ってみることができればじゅうぶんです。ところが、基本的な想像力が身についていないと、それだけのことがなかなかむずかしいのです。(p.143)
これは私なりに表現すれば「他者の視点の獲得」である。または、著者がいうところの「メタ認知能力」とほとんど同じ意味だろう。
我々は物語を読むとき、主人公や語り手の意識に入り込んでものを見ることになる。が、それと同時に、自分が他人の意識に入り込んでいることも一段上の意識では感じ取っているのである。
この俯瞰的な、あるいは反省的な意識の形成は人間を大きく成長させる。
2-4-3.全体を見渡して論理的に考える力
最後に、著者は実体のある本との付き合いが「全体感」を育むことを指摘する。
どういうことかというと、自分の興味のままに図書館や書店に通って書棚のあいだを歩きまわってみると、自分の関心の周辺にある本まで目に入ってくる。自分の問題意識は孤立していないことがだんだんと掴めてくる。そして自分がいかにその問題にたいして無知であるか実感されてくる。
これはつまり、自分と問題意識との間にある距離感を掴むということなのだ。
着地点も見えないのに走り出すのは苦しく、空しい。たとえ幻想であってもゴールは常に視界に入っている方が、知的好奇心の維持・持続という観点からも健全であろう。
2-5.番外編「紙の本を読みなよ」
補足的に、「本」というメディアそのものについて言及しよう。
私は前回のブログ(【書評】フレドリック・ブラウン『さあ、気ちがいになりなさい』【ユーモアとアイデアの傑作SF短編を解説!(ネタバレ注意!)】)で、とあるアニメキャラのセリフを紹介した。
 槙島聖護
槙島聖護
2-4-3でも述べたこととも関連するが、脇 明子 氏は基本的には紙の本を優れたメディアであると認識している。それは「本」と「コンピューター」を比較をすることで導き出されているのだが、この部分は、デジタルネイティブ世代に近ければ近いほど、古い議論に感じられる点でもあるだろう。
インターネットの功罪や画面上で読むテクストの是非を論ずるには、脇 明子 氏は世代が上過ぎるというのが私の感想だ。が、そこに見るべき意見がないわけではない。
「本」と「コンピューター」の比較部分(p.150)をまとめると次のようになる。
- 本
・一度に見られるのは見開き2ページだけだが、手でぺージをめくれば繋がりが実感しやすい
・本の厚みなどから「どこまで読んだ」「全部読み切った」というように進捗状況を確認することができる - コンピューター
・マウスをクリックして出すページとページの繋がりは分かりにくい
・情報資源全体のうち、自分がどれだけに目を通したのか全然つかめない。マウスをクリックしているとしょっちゅうもとの画面にもどってしまい、そこからまた出直すので、まるで見通しのきかない迷路のなかにいるよう。
ついでに、「床が抜けるほどの蔵書」を持つ稀代の読書家・井上ひさしの『本の運命』でも同じようなことが述べられているのでご紹介。
電子ブックでも本でも、入っている情報は同じものかもしれません。ただ、本はそれだけじゃない。活字の組み方、ページをめくる感触、持った時の重さ、そういったものをすべて含めて本と言ってるわけです。
本というのは、実はコンピュータにも匹敵するすぐれた装置だと思っています。目次があり、見出しがあり、パッと開けば自分の読みたいページが出てくる。(略)
じっくり読みたい時はゆっくりと読める。あるいは、この先どうなるかと心が急く時は、どんどんページを繰っていく。これは電子ブックにはないんです。「ページ風を立てる」という言い方がありますが、これは電子ブックではどうやってもできない。特に小説にいたっては、最初の一行から最後の一行に至る作品が作り出す時間の流れというものがあります。それは電子ブックだと見えないんですね。うまく言えないんですけど、全体が見通せないというんでしょうか⋯⋯。(pp.176-177)
これらの「本は読書の進行具合が確認できる」という指摘は、個人的にはまったくその通りである。
私は本を読み始めるとき、その本の厚さ、章ごとの枚数、どこで物語が終わるのか、必ず確認し付せんで目印をつける。そして読み始めてからも今読んでいるのは全体(または章)のうちどのあたりか、というのを常に掌で感じながら読み進める癖がある。
小説でも学術書でもその他どんな本でも、展開のテンポというか、構造がある。それを掴むためには物質としての本の作りが大いにヒントとなるのだ。これが作品を鑑賞する上で非常に有益な情報なのである。
というと、私が諸手を挙げて「本」を称賛しているように映るかもわからないけれども、現代における潮流はむしろインターネット情報資源の爆発的な増大であることも理解しているつもりだ。それは図書館情報資源を勉強してよくわかった。
実際私も、今や論文、ブログ、Webサイト、ソフトフェア、メール、SNSなど紙上ならぬ画面上で読むテキストの量は本のそれをはるかに超える。それはまた、求める情報へのアクセシビリティが著しく向上していることも意味している。
だから、物質としての「本」の擁護は「本を読み始めたばかりの子どもたちにとって」という視点からであることを読者諸賢には言い添えておく。
3.まとめ―読書を薦める本のジレンマ

この本で述べられていることは、私に言わせれば「読書とは(物語世界を)体験的に生きることである」という言葉に収斂する。
この読書哲学は、坂口安吾、安部公房、吉田健一などの偉大な文学者たちが繰り返し論じていることである(機会があればそれぞれについてもいずれ記事を書こう)。
だから私にはとてもすんなり受け入れられる内容であった。なにより本書は敬体の文章で分かりやすく、長年の児童研究で得たであろう柔らかく暖かな視点と知見に裏打ちされた、充分な説得力で提示されている面白さがある。
最後に、脇 明子 氏の児童文学観が極めてわかりやすくにじみ出ている一説を、他の作品(『少女たちの19世紀 人魚姫からアリスまで』)ではあるが引用して擱筆することとする。
子どものために書くには、子どもにわかるやさしい言葉で書かなくてはなりませんが、そんな言葉で物語の舞台や登場人物について説明し、出来事を筋道に沿って目に見えるように語り、風景描写や心情表現などもやってのけるというのは、けっして楽な仕事ではありません。やさしい言葉で書くからといって、中身の薄いものになってはだめなのです。(略)本当に優れた児童文学は、言葉がやさしくて短くても、隅々まで神経が行き届いていて、驚くほど中身が濃くて、おもしろいのです。(『少女たちの19世紀 人魚姫からアリスまで』第2章より)