「さあ、気ちがいになりなさい」
- 独創的な海外SFを読みたい!
- 切れ味のあるオチがある小説が好き
- 「狂気」に関心がある
むやみに「カシューナッツを食べたいなあ」と思うのと同じように、なんとなく「SFな気分になる」ということは誰にでもある(少なくとも私にはある)。
そんな気分でつい先日、NETFLIXでたまたま目に留まったSFアニメ「PSYCHO-PASS」(第1期全22話)を一気に鑑賞してしまった。リアルタイムで放映されていた2012年以来の視聴である。
当時も「めちゃくちゃおもしろいなあ!」とすっかりハマっていたけれど、改めて見てもその思想性・哲学性、キャラクターの魅力、絵、ストーリーどれをとってもよく作りこまれていて傑作だと感じた。
このアニメはある種のディストピア、つまり人間としての自由な選択を失い、計量的データによってはじき出された「幸福」を押し付けてくる社会を描いた近未来SFである。
舞台は、人間のあらゆる心理状態や性格傾向の計測を可能とし、それを数値化する機能を持つ「シビュラシステム」という「包括的生涯福祉支援システム」が導入された西暦2112年の日本(もっぱら東京)。
人々はこの値を通称「PSYCHO-PASS」と呼び習わし、有害なストレスから解放された「理想的な人生」を送るための指標としていた。
大衆は盲目的にシビュラによる判定(職業適性考査)を受け入れ、疑いもせず提案された道を歩む非人間的な人生を送るようになり久しかった。
主人公が「厚生省公安局刑事課一係」に配属された初日を境に、その絶対的な社会制度を揺るがすような事件が連鎖的に起きる。
そして、その犯罪の中心人物として浮かび上がってくるのが「槙島 聖護」という男であった。

出典:アニメ「PSYCHO-PASS」HPより
彼がこのアニメでどのような役割を果たすのかは皆様自身でご確認いただくとして、彼は類まれなる読書家で、哲学への造詣も深いキャラクターとして描かれている。
その槙島聖護が第15話で次のような興味深い読書観を提示する。
 チェ・グソン
チェ・グソン
 槙島聖護
槙島聖護
 チェ・グソン
チェ・グソン
 槙島聖護
槙島聖護
 チェ・グソン
チェ・グソン
 槙島聖護
槙島聖護
 チェ・グソン
チェ・グソン
 槙島聖護
槙島聖護
 チェ・グソン
チェ・グソン
 槙島聖護
槙島聖護
精神的な調律、チューニングみたいなものかな。
調律する際大事なのは、紙に指で触れている感覚や本をぺらぺらめくったとき瞬間的に脳の神経を刺激するものだ
ここで語られていることを私が重要だと思うのは、槙島聖護が「身体性」を強調しているからだ。
紙の本を読むとき、掌は本の質量を感じ、指先は紙の表面のつるつるした質感を感覚している。
もっと言えば、その本を読んでいる自分の身体は、例えば夜の薄暗い書斎にあって、窓の外を走る車のブウウウンという低いエンジンを遠くに聞いていたり、あるいは朝の満員電車で隣のOLと肩が触れあうのを感じていたりする。
そういう物理的な空間のなかで、本来意識は静かに目の前の本の内側で展開される内容に向かうべきところを、他の対象に向かっている。
人はそういう時間で落ち着いて自己に向き合うことで、日々怒涛のように押し寄せる状況・情報・感情の波で乱れた精神を整えることができるのだ。
つまりこれは「マインドワンダリング(mind wandering)」が創造性や精神的健康に寄与するということの具体例なのである。
参考 参考論文J-STAGEトップ/社会心理学研究/36巻(2020)3号まあ、ポイントは目の前の作業にそれほど集中する必要がなく意識を遊ばせておけるということであり、行為としては読書ではなく、絵を描いたり、ウォーキングや星を眺めることでもいいのだけれど。
閑話休題。
前置きが長くなったが、今回紹介するフレドリック・ブラウン『さあ、気ちがいになりなさい』もまた、「PSYCHO-PASS」に負けず劣らず思索を誘う、抜群におもしろいSF短編小説集である。
「気ちがい」というなかなか美しい言葉が入っているタイトルからして目を引くこと只事ではない。
作者の概要など細かいことはすっ飛ばして作品鑑賞に入ってみればそのユーモアと着想の素晴らしさに感嘆すること請け合いである。
なお、本書の収録作品の邦題と原題、発表年は次の通り。
「みどりの星へ」(Something green),1951
「ぶっそうなやつら」(The dangerous people),1951
「おそるべき坊や」(Armageddon),1941
「電獣ヴァヴェリ」(The waveries),1945
「ノック」(Knock),1948
「ユーディの原理」(The Yehudi principle),1944
「シリウス・ゼロ」(Nothing Sirius),1944
「町を求む」(A town wanted),1940
「帽子の手品」(The hat trick),1943
「不死鳥への手紙」(Letter to a phoenix),1949
「沈黙と叫び」(Cry silence),1951
「さあ、気ちがいになりなさい」(Come and go mad),1949
さて、以下では私が特に興味を覚えた5作品をランキング形式で紹介しよう。
予備知識なしで『さあ、気ちがいになりなさい』を読みたい方は、読了後また戻ってきてください。
おすすめ第5位.「シリウス・ゼロ」
pp.169-203(34ページ)
この作品はいわゆる「ファーストコンタクトもの」である。つまり、未知なる惑星の生命体との邂逅をユーモラスに描いている。
主な登場人物は、シリウス主星の2つの惑星ソアとフリーダを興業回りしている一家(自分=語り手:ウェリー、妻、娘:エレン)と、宇宙船の操縦士ジョニー・レーン。
ソアとフリーダには地球からの開拓者が住んでいて、彼らは「死ぬほど娯楽に飢えている」。そこへウェリーの一家は「ロケットゲーム」を提供していた。
宇宙船内、ソアでボロ儲けしてほくほくのシーンから物語は始まる。
ソアの軌道内を航行中、ジョニーが別の惑星を発見し浮足立つ一行。ソアはシリウスの第一惑星であり内側には惑星などないはず。つまり、われわれが新たな惑星の第一発見者だ。ゆえに命名権がある!
第一惑星よりも手前にある惑星だから「シリウス・ゼロ」やな! そんな真剣みを欠いたノリでウェリーが言う。そして着陸する。
緑の丘に降り立つ4人。そこへ、恐るべき光景が現れた。丘の向こうに象より大きい駝鳥のような動物の頭がのぞいた。その生物の細い首には水玉模様の蝶ネクタイが巻かれ、鮮やかな黄色い帽子をかぶり紫の羽飾りまでついていた。
ウインクして消えたそれにしばし言葉を失うも、一行は冒険を始める。やがて、人工物としか思われない舗装道路が現れた。不審に思いつつも進んでいくと、今度はレンガ造りの建物があり「レストラン」と表記されていた。
ウェリーがその建物を見るとそれは映画のセットのように表面だけしかなかった。その裏側の地面に昆虫の巣のような穴を見つける。黒い油虫がいる。
これまでヘンテコなものしかなかった惑星で、唯一その油虫は何の変哲もなかった。つまり、何も変わっていない点で変わっていた。
4人はさらに次の丘まで舗装道路を歩いていく。すると大きなテントが現れ、そこにはゲームセンターの旗が立っていた。中に入ると、ウェリー夫婦の旧友サム・ハイデマンという男がいた。彼と共に、絶世の美女で映画スターだというミス・アンバースもいた。
彼から話を聞くに、どこぞの映画会社が撮影場所にするため、この無人の惑星を内緒で買い上げたのだという。つまり、本当に映画のセットだったと判明した。
サム・ハイデマンは彼ら一行にこの惑星のことを口外しないでもらうのと引き換えに「最高のおもてなし」をするという。そのおもてなしに相応しい服装に着替えるため、一行は一度宇宙船へ引き返す。その途中、ウェリーは何か違和感を感じていた。
宇宙船への帰り道、また表面だけのレストランに戻ってきて休憩がてら葉巻で一服していた。おもむろにウェリーは例の油虫を踏みつぶそうとして逃げられる。
そのとき、彼は違和感の正体に気づいた。
「サム・ハイデマンは数年前にもう死んで…」
その瞬間、寄りかかっていたレンガ造りの建物も目の前に伸びていた舗装道路もパッと消え失せてしまう。
4人は大急ぎで宇宙船に戻る。そこで、どこからともなく声が聞こえてきた。
その声がだいたい次のような興味深い議論を展開する。
君たちはもう二度とこの星へ来るべきではない。なぜなら、そちらと我々の文明は違いすぎる。
我々は君たちの心の中にあるイメージを具現化して研究した。あなたたちが見たのはすべて我々が作り出した幻想である。
そして分かった。君らの文明は物に関心を抱くタイプだが、わたしたちは精神に関心を持つ。そんな我々が付き合っても互いに得るものはない。何よりこの星には君たちの惑星の役にたつような物質は、なにひとつない。
そして、その声の正体があの、この惑星で唯一何の変哲もない「油虫」であることが明かされる。
その声は続ける。
「……ところで、ここがおたがいにどうも打ちとけ合えない点です。はっきり申しあげますと、わたしたちを見てそちらが気持ち悪くなるのと同じに、こちらから見るとあなたがたはどうも気持ち悪くてたまらないのです」(p.200)
そうしてウェリーたちはシリウス・ゼロを離陸したのであった。
————————–
私がこの作品を読んでまっさきに連想したのはスタニスワフ・レムの大傑作SF小説『ソラリス』(1961)である。
「シリウス・ゼロ」の方が『ソラリス』よりずっと軽く、ユーモラスだが、人間の(潜在)意識をあぶり出し物体化させる他惑星の生命体との邂逅というアイデアは共通のものがある。
それから、人間という存在が他の生物(ここでは他惑星の生命体)から見たらいかに醜悪かという視点は皮肉の天才スウィフトの代表作『ガリヴァ旅行記』も彷彿とさせる。
おすすめ第4位.「ノック」
pp.117-137(20ページ)
次に紹介する「ノック」は技巧的に優れた作品である。
まず、これ以上ないほどかっこいい書き出しを引用する。
わずか二つの文で書かれた、とてもスマートな怪談がある。
「地球上で最後に残った男が、ただひとり部屋のなかにすわっていた。すると、ドアにノックの音が……」(p.117)
いかがであろうか? これほど物語の続きをあれこれ想像させる書き出しはちょっとお目にかかったことがない。
「え?え?地球上のほかの人類どうした? ていうか最後の一人なのに、だれがノックしてきてんの…?」という疑問が瞬時に頭を駆け抜ける。
ちなみに英語では “The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door…” となっている。
“The last man on Earth” を「地球最後の人間」とも「地球最後の男」とも読めるのが肝なのだと思うのだけれど、翻訳ではさすがに表現できない。
ちなみにその次には
「二つの文章と、点を並べた省略を示す符号だけ。この話のこわさは、もちろん二つの文のほうにはない。それは省略の符号のなかで暗示されている。いったい、なにものがノックしたのだろうか。わけのわからない状態にであうと、人間の心は、ちょっといいようのない恐怖におそわれるものだ。
だが、実際のところは、恐怖にみちたものではなかったのである。」(p.117)
と続く。
これで読みたくならないわけがない。
かつて太宰治が「女の決闘」という作品の中で森鴎外の翻訳小説から優れた書き出しを列挙し褒めていたが、そこに混じっていてもおかしくないほどである。
物語の構造としても凝っていて、最初に部屋を「ノック」してきたものが人類にとっての絶望を表わしていながら、最後には希望に満ちた「ノック」へと見事に転換される。
まるで郊外の薄暗い廃墟で人知れず講演される闇のサーカスの手品のようである。
おすすめ第3位.「みどりの星へ」
pp.9-26(17ページ)
この作品はある種の「正気と狂気」をテーマにした作品である。それだけでもう、人間の精神に少なからぬ関心を抱く私としてはおもしろくないわけがないのである。
この物語の主人公は、目に入るすべての事物が真っ赤な惑星に不時着した宇宙飛行士マックガリー。
彼は一人、孤独に冒険を続けてもう5年以上の月日が流れていた。目的は以前何かで読んで頭の片隅に残っていた、過去に同じくこの惑星に着陸した宇宙艇であった。その宇宙艇が再び離陸したという記録がなかったことから、自分の宇宙艇の修理に必要なパーツを調達しようと考えていたのだ。
彼はその孤独のなかで出会った、大きさも重さも女性の手のような5本脚の生命体を肩に乗せていた。彼は彼女(女性の手みたいなので女性性ということにした)を「ドロシー」と名付け、返事もないのに呼びかけることで正気を保っていた。
皆さんも想像してみてほしいのだけれど、人は真っ赤な世界でどれだけ気が狂わずにいられるだろうか?
このCMは様々な都市伝説や「トラウマCM」などというレッテルを貼られて流布しているけれど、その理由を私は「真っ赤さゆえ」だと思っている(適当)。
彼は赤い世界の中にあって自分の故郷である地球に溢れる「緑色」を渇望していた。
赤の惑星には奇怪な猛獣がいて、そいつから身を守る武器として「太陽銃」(太陽で充電でき、弾がいらない)を携帯していた。その太陽銃から発せられる光線が唯一の「緑」であり、彼にとっての癒しであった。
ある時、遥か彼方の上空を1隻の宇宙艇が飛ぶのが見えた。マックガリーは必死に合図を送った。それを見とめた宇宙艇が降り立ったとき、彼はようやく助かったと安堵した。
その宇宙艇に乗っていたのは宇宙パトロールのアーチャー中尉という青年であった。
二人は地面に腰掛けて話をする。マックガリーは赤の惑星での日々を彼に語って聞かせた。聞いているうちにアーチャーの表情が曇りだした。
そして彼は静かにマックガリーへ「真実(というか現実)」を伝える。
不時着した年から計算するとあなたが彷徨っていた期間は5年ではなく30年であること。
探していた過去の宇宙艇は、この赤の星(クルーガー第三惑星)ではなく第五惑星に降り立っていたこと。(=いくら探しても見つかりっこない)
あなたの肩には「ドロシー」など乗っておらず、孤独が作り上げた妄想であったこと。
そして…あなたが帰ろうとしてる緑の星・地球は20年前に他惑星との戦争で黒焦げになって滅びてしまったこと。
一見するとマックガリーは落ち着いてそれらの事実を受け止めたかに見えた。そしてアーチャーはそろそろ出発しようと言い、立ち上がって宇宙艇のほうへ歩き出しだ。
その瞬間、マックガリーは緑の光線を放つ太陽銃でアーチャーと彼の宇宙艇を跡形もなく消し去ったのだった…!
そして彼は、ドロシーと共に赤の惑星の旅へ再び出ていく。地球へ戻るための部品探しのために。
————————–
この作品から読み取るべきなのは人間の精神の働き、厳密にいえば「自我」の自己保存である。
自我については「【精神分析】「嫉妬」の構造【正体を解説!】」という記事の中で基本的なことは説明しているが、改めて簡潔にまとめてみよう。
精神分析学における「自我」は現実へ適応するための装置であるとされる。
動物が持っている本能とは異なり、「自我」は生物学的基盤を持たず(つまり自分の身体から必然的に滲み出てくるようなものではなく)、生後後天的に構築されるがゆえに壊れる可能性がある。
「自我」がなければ人は生命を維持するための行動がとれないので守らなければならない。
ヒトを含めすべての動物に自己保存のエネルギーはあるが、ヒトの場合それが「自我」の保存に方向づけられている。
自我は必ずしも生命=身体的存在と一致していないので、自我を守るために現実的な立場を危うくしたり、場合によっては死を選ぶということも起こり得る。
分かりやすい例でいえば、第二次世界大戦中の日本軍における「神風特攻隊」。その行為の倫理的・道徳的判断はここではどうでもよい。重要なのは、当時の若者の自我において、「鬼畜米英」に負けて「亡国」してしまうより、自らの命を投げうってでも奴らにダメージを与えたい! という観念がリアリティーを持っていたということである。
この時代状況で彼らが直面したのは、「自我」を守って生物学的生存を失うか、「生物学的生存」を守って自我を失い廃人と化すか、という二律背反であった。
「渇しても盗泉の水を飲まず」(どれだけ貧しても不義不正に手は出さない)という故事があるが、これも同じ。どんなに喉が渇いても、「盗水」などという名の泉の水は飲まない。つまり、生命の維持にかかわる生理的欲求でさえも、倫理を侵すような(またはそれを連想させるような)真似をしてまで満たしたくはない。
こんなことは地球上すべての動物の中で「自我」を持つ人間にだけ起こりうることである。
現代日本という恵まれた環境を生きる我々には自我と身体的生命との間にここまで極端なズレはないけれども(つまり自我の行動規範に従って行動すれば、現実的な生命も守りつつ、社会的な位置付けも守れる)、状況さえ整えば人は案外容易に「自我」を守るため生命を投げうつことができるという例である。
ここから、マックガリーの最後の行動の意味も見えてくる。
彼の自我は「真っ赤な惑星での孤独」という直視しがたい絶望的な「現実」の認識とその状況への適応ができるような形になっていた。
帰還すべき地球も、若さも(不時着して5年しか経っていない)、過去の宇宙艇(修理部品が調達できるという希望)も、ドロシーも、マックガリーの幻想(それは心的現実とも言える)の中でだけは確実に存在していた。
そして「他者」が不在となれば自分だけの現実こそが唯一客観的な現実となる。
それを守るためには、アーチャーが示したもう一つの現実など邪魔でしかなかったのだ。だから、アーチャーと共に宇宙艇に乗って自分の生命を実際的に救うよりも、彼を自分の世界から抹消する道を選んだ。たとえそれが、身体的には「死」へ直結する選択肢であったとしても。
いかがであろう! 精神分析的観点から実に示唆に富む一本だと思いませんか。
おすすめ第2位.「ユーディの原理」
pp.141-165(24ページ)
なにかを「おもしろい」と思うとき、それは客観的におもしろいなどということはあり得ない。
「おもしろさ」は常に自分との関わりにおいて、つまり自分が持つ何らかの価値観と繋がりを持つがゆえにおもしろいのであって、いつの時代でも誰にとっても普遍的におもしろいなどということはない。
小説に限っていえば、それが物語の内容なのか、文体なのか、語り口なのか、言葉選びなのか、その他様々な観点があり得る。
で、本短篇集内で技巧的にもっとも高度なのがこの「ユーディの原理」だと個人的に思う。もっといえば「構造」こそがこの作品のおもしろさである。
語り手の「私」(小説家)が工科の学生時代の友人チャーリー・スワンのへんてこな発明について聞くところから物語は始まる。
チャーリーは鉢巻き型の装置を頭にぴったり巻き付けていて、「その機械にできそうなことは、せいぜい頭痛をなおすか、それとも、ひどくでもする以外になさそうだった」。(p.142)
主人公は
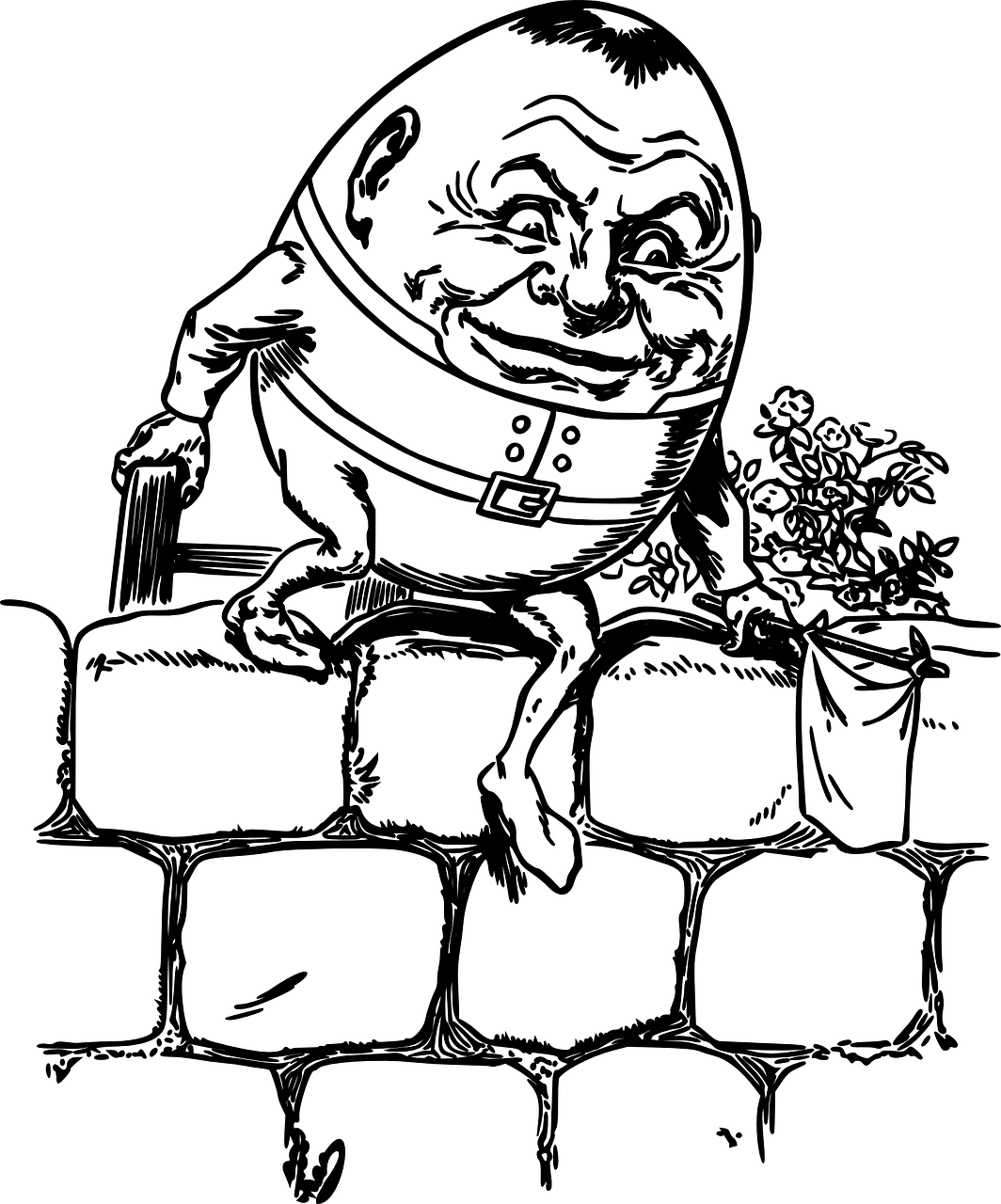
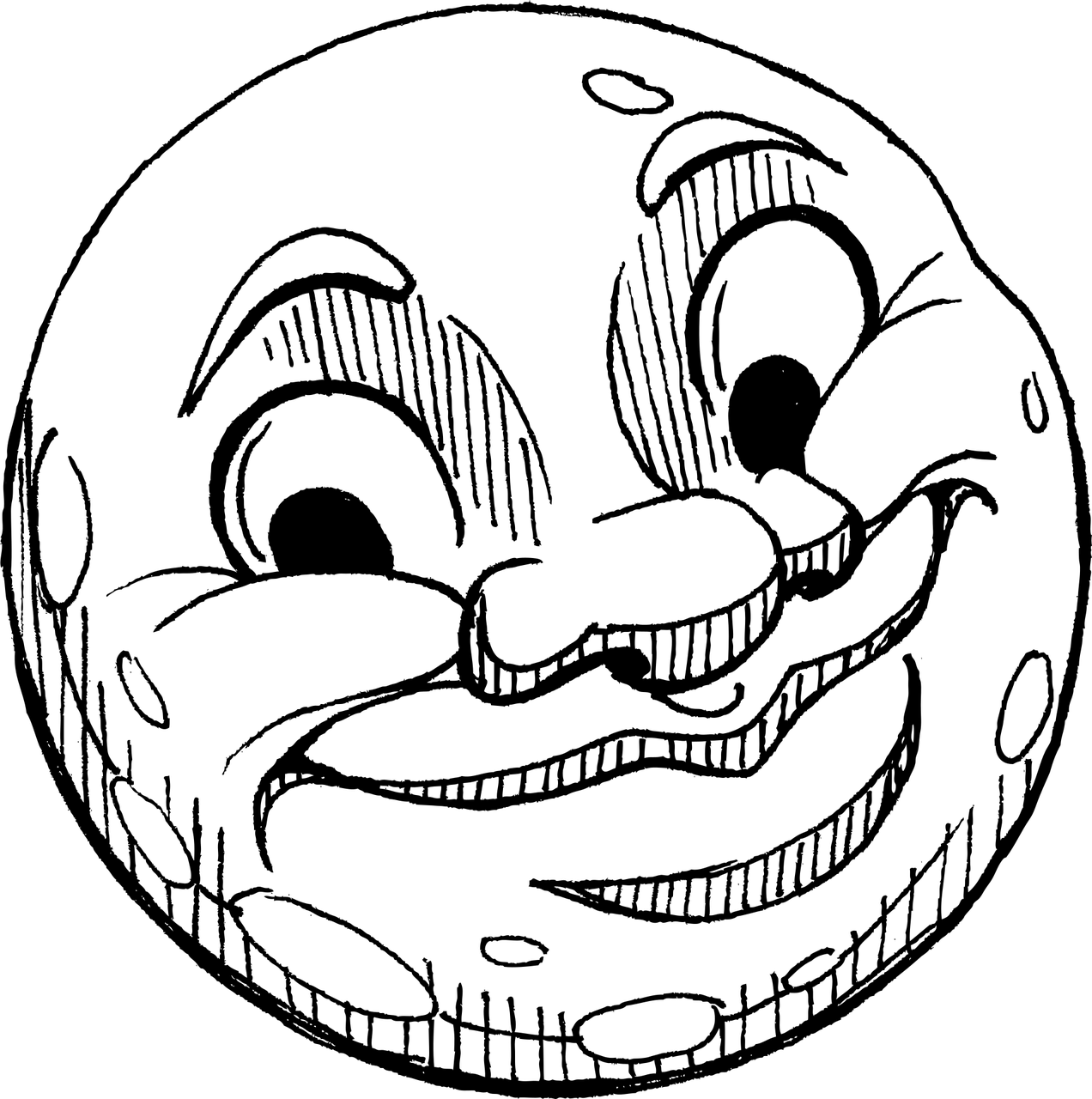
主人公は「なにいっとんじゃこいつ?」というテンションである。いわく、ビルを移したり機関車を持ってきたりするような常軌を逸したことは不可能だが、ちょっとしたことなら望みどおりにやってくれるという。
「どんな原理なの?」
チャーリーは「ユーディの原理」と答える。「ユーディ」とは当時の俗語で「そこにはいない小人」を指すらしいが、その目に見えない小人が命令を聞いてくれるという友人なりの冗談であった。「ユーディがやってくれるんだ」
主人公は、そんなら酒を持ってきてみろ、とチャーリーに言う。チャーリーは頭をちょっと下げる。すると一瞬、彼の姿がぼやけた。と、そう思ったときにはすでに元に戻っていて、酒が用意されていた。主人公は驚く。「この発明は金持ちになれまっせ!!」
酒を飲みながら、チャーリーは「私」にその装置を使ってみてくれという。自分の脳にだけ反応しているわけではないことを確かめたい、と。で、「私」も実際に試してみる。またしても一瞬であらたに酒が用意されていた。
テンションの上がる「私」は言う。この機械がなんでもやってくれるというのなら、一つ美人女優でも召喚してパーティーをやらかそうか!
それに対して、チャーリーは「それは無理」と言う。そしてその装置の本当の原理を説明する。
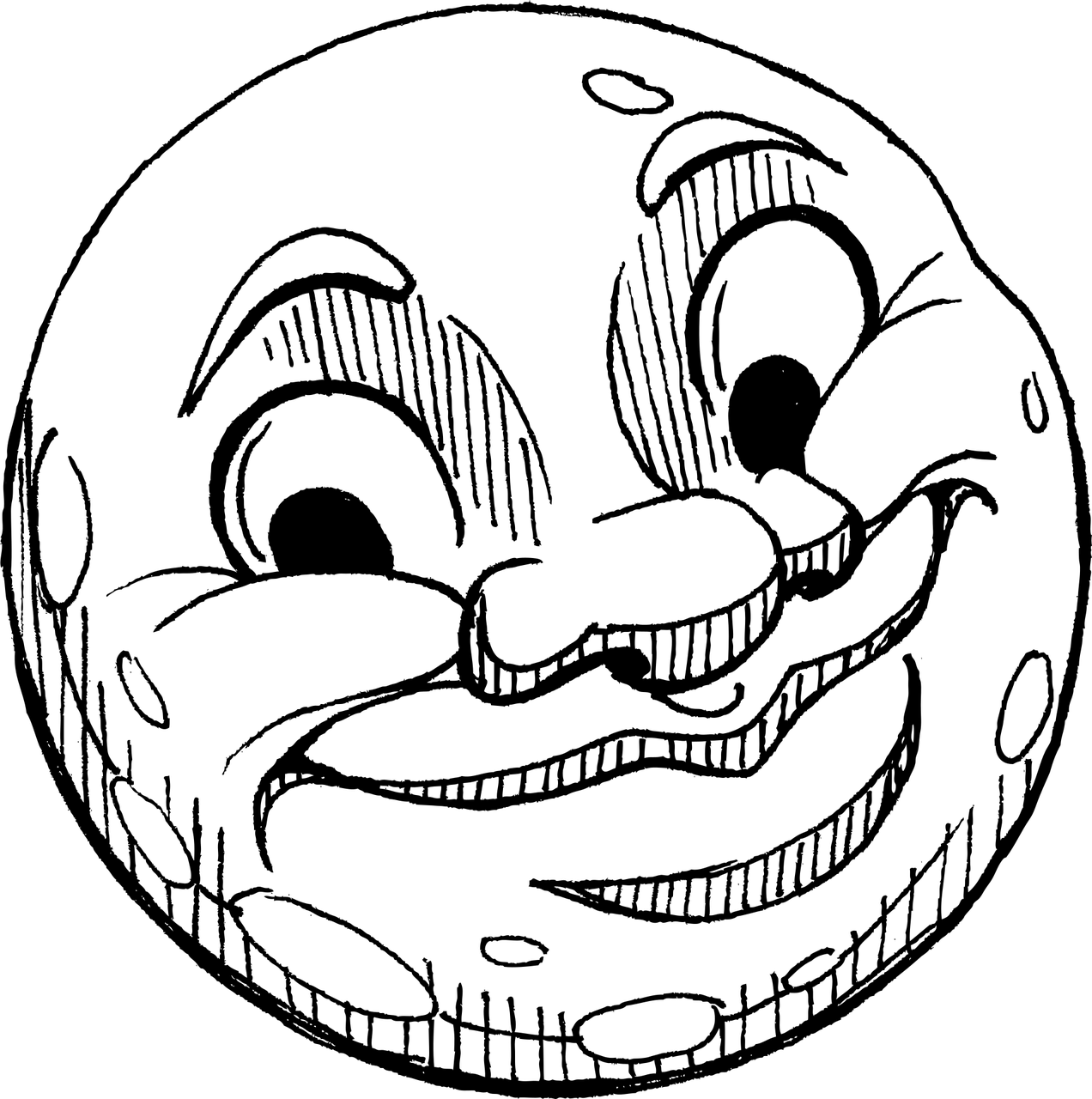
なんのこっちゃよく分からない「私」に対し、チャーリーは大体次のように説明する。
- 装置が細胞の運動を数千倍に早める。脳の働きと体の動きが電光石火のごとく早められる
- スイッチ(軽いお辞儀)が入る直前の命令が自己暗示となり、自分がその通り動いているのだ
- そのスピードが速すぎるために誰にも動作は見えず、結果のみが提示される。まるで実在しない小人がやってくれたように
- ただし、記憶力だけは加速の影響を受けないので自分は何も覚えていない
じゃあ、と「私」はいう。「この酒はどこから持ってきたのか?」
チャーリーは「その辺の飲み屋からだろう」という。財布を見ると5ドル消えている。記憶こそないが、きちんと払ってきたんだろう、と。
だとしたら、これはあくまで自分にできることしかできないのだから、大してすごくもないんじゃないか?
それに対し、チャーリーはこの装置の本当の用途を解説する。つまり、急いで片付けなくちゃいけない仕事、あるいは、したくないけれどもやらなければならない仕事。そういう類を苦痛なくやっつけるためのものなんだ。
「私」は食い気味で言う、「小説を書くなんてことでもか」
そして「私」は実際にそれを実行する。一瞬のうちにタイプライターの横に紙が束ができていて、最後に打ち出された文字は《終り》だった。まさに大発明であった。
いい気持ちで酔った二人はこんな会話をする。
めんどくさそうな「ああ」という答え。というより、チャーリーはそう言うつもりたのだが、じっさいには「にゃあ」と聞こえた。
「チャーリー。酔ったな。どうだ、もっと使ってみてもいいか」
「かってに死ね」
「なんだと。ああ、そうか、かってにしな、と言ったんだな。よし、 それじゃ……」
「そうだ。 ふう……。 そう言ったさ。かってにしろ、とな」
と、チャーリーはろれつが回らなかった。
「そうじゃ、ないようにも、聞こえた」
「じゃあ、なんと、いったのかい」
「きみあ、こう言いた—―いや、言った。かってに死ね、とかなんとか」(pp.157-158)
その時、ズドンという銃声がした。「私」とチャーリーは飛び上がった。もしかしたら、「私」はこの装置をしたまま「かってに死ね」という命令を自分に下してしまったのではないか…?!
だが実際には彼にケガはなかった。というか、銃声はその部屋ではなく廊下から聴こえてきていたのだった。一気に酔いの冷めた二人が急いで見に行くと、火薬の焼け焦げた匂いだけがあたりに漂っていた。そして「私」は悟る。
「チャーリー。あれはユーディだったんだよ。おれが〝かってに死ね〟と言ったとき、振子が揺れたんで、自殺しちまったんだ。きみはまちがっていた。自動―——自動制御自己暗示式なんとかかんとかじゃないんだ。いままでもずっと、ユーディがやってたんだよ。あれは……」(p.159)
現にその装置は、チャーリーが見たところ何も故障していないにもかかわらず二度と作動しなかった。「そんなアホな…。おれは科学的な原理にのっとって作ったんだぜ」
そう呟くチャーリーを横目に、「私」はふと思いついてタイプライター台に近寄って例の小説原稿をとりあげた。
そこに書かれている題は、『ユーディの原理』だった……
————————–
今読者が実際に読んでいる目の前の文章はどのようにして書かれたのか? を説明することによって、フィクションと現実世界が見事に接続されるという複雑な手法に、私は舌を巻くばかりである。
少し煩雑なので、改めて簡潔にその構造をまとめてみよう。
位相1:現実の読者(我々)が「ユーディの原理」という短編小説を読んでいる
位相2:その小説の中で「ユーディの原理」で動く装置が登場⇒「ユーディ」という目に見えない小人の力によって小説が書かれる
位相3:位相2の登場人物たちが読む小説に、今まさに自分たちが経験した・することが書かれてある。つまり、我々現実の読者が読んでいるこの小説を、その小説内の登場人物も一緒に読んでいる。
お分かりいただけるであろうか? 自分が読んでいる小説の中でさらに小説が書かれ、その書かれた小説が実は自分が読んでいる小説だった、というまるでエッシャー(私が大好きな画家の一人)のだまし絵みたいな構造なのである!

出典:ベネディクト・タッシェン出版「M.C.エッシャー グラフィック」より
こういう円環性というか、メタ的というか、物語世界と現実が地続きだと感じさせる感覚がたまらない。
我々の生きるこの現実が物語世界の延長なのだとも思えるし、物語世界もまた現実の一部なのであろうと思える。世界に境界線はない。
似た手法・構造の小説として、森見登美彦『熱帯』と児童文学の『ダレン・シャン』シリーズをおすすめしておく。
おすすめ第1位.「さあ、気ちがいになりなさい」
pp.269-356(87ページ)
さて、おすすめの堂々第1位は、表題作「さあ、気ちがいになりなさい」である。
この短編集の中では一番長い話となっていて、全部で8章に分かれている。これも「みどりの星へ」と同様に「正気と狂気」がテーマになっている作品だ。あるいは、「自分とは何か?」というアイデンティティー論を考える物語でもある。
思うにフレドリック・ブラウンという作家は、自分自身もまた「現実」に違和感を持っていた人ではないだろうか? いずれにせよ、私はシンパシーを感じずにはいられない。
さて、本作品の主人公ジョージ・バインは、30歳の英国人で、記者である。
彼は3年前に事故にあって大けがをした。気が付いたとき、「ナポレオン」となっていた。これは比喩ではなく、文字通りナポレオンとして27年生きた記憶と共に見たこともない白い部屋で目覚めたのである。
自分は気ちがいになったのか? いや、どうもそうではないらしい。私に声をかけてくる連中はみな「ジョージ・バイン」と呼び掛けてくる。そう、実際自分には20世紀イギリスの知識がある。フランス人の私がなぜ聞いたこともないこの時代の英語を理解できるのか、「自動車」のイメージが心に浮かぶのか。
全くわけがわからなかった。そこから彼は、自分をナポレオンと思い込んでいる偏執狂として精神病院にぶち込まれないよう、「記憶喪失症」を装ってひとまずジョージ・バインとしてやっていこうと決めた。そうしてなんとか3年が過ぎていた。
そんな彼はある日編集長に呼び出され、特別に取材を頼みたい仕事があると持ち掛けられた。
編集長によると、ランドルフという精神病院の院長からの依頼で、社でも最も腕利きの記者を派遣してほしいとのことであった。自分の院内で起こっていることが本当なのか、取材してほしい、真偽のほどが明らかになったら貴社の一面のトップに掲載していいから、と。
バインは「なにをするんです?」と編集長に問う。
すると編集長は、取材の条件を告げる。「精神病者のふりをして病院に潜りこむこと」
それを聞いてバインは腹を立てながら断る。理由は明白であった。
なぜこの仕事を自分にやらせたいのか? 編集長は3年前自分の身に何が起きたか知っているのではなかったか? 自分は30歳ということになっているが、それに確信が持てない。自分の記憶はここ3年分しかないからだ。
事故にあって以来記憶喪失症が治らないままなのだ!
しかし自分の過去は知っている。10年前に入社したこと。どこでいつ生まれたか、死んでしまっている父や母(写真を見せられたから)のこと、自分に妻子はないことも知っている。けれど、ここが問題だが、全て人から聞いて知っているだけなのだ。しかも自分が知らないみんなから。
編集長はいま、そんな自分の精神についてどれだけ自信が持てるか分からない人間に対し「気ちがいの患者になりすまして精神病院へ潜りこめ」などと命令した! あんまりではないか!
それでも、結局ジョージ・バインはその仕事を引き受けることする。なぜかというと、その仕事の合間に最新の衝撃療法を施してもらえる、という隠れた条件があったためだった。記憶が戻る方法があるなら試したいのが人情だ。
「で、私はどんな種類の精神病になっているふりをすればいいんですか」とジョージ・バインは問う。すると編集長が答える。
「ナポレオン妄想」
つまり、人知れずナポレオンの人生の記憶しまい込んでそれを必死に隠して生きている男に対し、こともあろうに、精神病院へ行ってこう主張せよという。
「ぼくはナポレオンです」
————————–
ここまでが2章分の展開である。そこからナポレオン妄想の「ナポレオン」がどうなるのかというと、宇宙規模のぶっとんだ物語へ発展していく!
おもしろそうだとおもったらぜひ読んでみたらいい。
正常か異常か、精神病、全能性、「私」とは、記憶が自分か、他者からのセルフイメージが自分か。
自分はジョージ・バインなのか、ナポレオンなのか?
結局、「私」とは「私」に関する記憶の総体なのであろうか?
そんな哲学チックな思索と物語のおもしろさに刺激を受けること間違いなしだ。
(このあたりのアイデンティティ・クライシスの問題はフィリップ・K・ディックがしばしば追求しているテーゼだ)
おわりに

取り上げた5作品に何か感じるものがあればぜひ手にとって読んでみてほしい。きっと期待よりずっとおもしろいから。それに、今回私のランキングに入らなかった作品も、秀逸なものばかりであることは保証する。
かつて日本を代表作するSF作家安部公房は自分の作品をして「仮説の文学」と称した。
それは、端的に言えば我々が信じて疑わないところの日常性、すなわち「常識」にヒビをいれてくれるような文学である。
言い方を変えれば、今ここにある現実を相対化する視点の提示だ。
今回紹介した『さあ、気ちがいになりなさい』がまさにそうだが、小説でもアニメでも映画でもよいSF作品というのは多かれ少なかれ「思考実験」の要素を持ち、それが我々の持つ常識や思い込みを揺さぶってくれる。
鑑賞し終えたあとでふとあたりを見渡すと、現実がそれまでと違った色を帯びて見える。そういう感覚を得たくて私は本やその他の作品を鑑賞している。
今、画面の向こう側でこの文章を読んでいるあなたはどうか?
もし惰性で繰り返しているくそおもしろくもない日常に一筋の清涼な毒を差し込みたかったら、『さあ、気ちがいになりなさい』。
【合わせて読みたい!】
 【書評】佐藤 究『Ank: a mirroring ape』——人類の起源に迫る自我意識の謎【魅力を徹底解説!】
【書評】佐藤 究『Ank: a mirroring ape』——人類の起源に迫る自我意識の謎【魅力を徹底解説!】
 【書評】木村敏『異常の構造』——正常/異常とはなにか?
【書評】木村敏『異常の構造』——正常/異常とはなにか?


